子育て世帯を支援する制度は、年々見直しや変更が行われており、2025年4月から新しい補助金が導入されました。
しかし、補助金や支援制度の種類が多いため、利用対象に該当しても気付けない人もいるでしょう。
この記事では、子育て世帯が利用できる補助金について、直近の変更点や新設された制度をまとめました。
- 2025年4月以降の子育て支援に関する変更点
- 児童手当等の補助金の申請方法や必要書類
- 補助金や支援制度を正しく理解するメリット
出産を控えている人や出産直後の人は、利用できる補助金があるか参考にしてください。
こども未来戦略により子育て世帯を支える補助金や制度が見直された

政府は2023年12月に子育て支援方針として、こども未来戦略を閣議決定しました。
こども未来戦略では、以下の3点を目標に子育てに関連する制度の見直しや新規制度の開設が行われています。
- 若者や子育て世代の所得を増やす
- 社会全体の構造や意識を変える
- すべての子どもと子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援していく
こども未来戦略の一環で、制度の見直しや新設された主な項目は、以下のとおりです。
- 児童手当の拡充
- 出産等における経済的負担を軽減
- 出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の創設
- 出産、子育て応援交付金事業
- 大学等の授業料等減免支援拡大
- こども誰でも通園制度
- 医療費等の負担を軽減
- 住まいの支援
補助金以外の内容も含めて、最新の子育て支援について確認しましょう。
児童手当は所得制限を撤廃して支給期間が高校生まで延長された
一定年齢の児童を養育する人に支給される児童手当は、2024年10月から以下の制度の見直しや変更が行われました。
- 所得制限の撤廃
- 支給期間を高校生まで延長
- 第3子以降の支給額の増額
- 多子加算の対象になる年齢の拡大
- 支払回数を年6回に増加
所得制限の撤廃により年収に関係なく一律の金額で利用が可能になり、支給期間は高校生まで延長されました。
以前の児童手当と2024年10月以降の児童手当の主な違いは、以下のとおりです。
| 以前の児童手当 | 2024年10月以降の児童手当 | |
|---|---|---|
| 所得制限 | あり | なし |
| 支給対象 | 中学生修了まで15歳到達後の最初の3月31日まで | 高校生年代まで18歳到達後の最初の3月31日まで |
| 第1子、第2子の支給額(月額) | 3歳未満:15,000円3歳から小学校修了まで:10,000円中学生:10,000円 | 3歳未満:15,000円3歳から高校生まで:10,000円 |
| 第3子以降の支給額(月額) | 3歳未満:15,000円3歳から小学校修了まで:15,000円中学生:10,000円 | 30,000円 |
| 多子加算の対象 | 高校生年代まで18歳到達後の最初の3月31日まで | 大学生年代まで22歳到達後の最初の3月31日まで |
| 支払回数 | 2月、6月、10月の年3回前月までの4ヶ月分 | 偶数月の年6回前月分までの2ヶ月分 |
※2025年7月時点
多くの養育者が利用できる補助金であるため、要件を満たす子どもがいる場合は申請しましょう。
出産育児一時金の見直しや生まれた直後に利用できる補助金が増えた
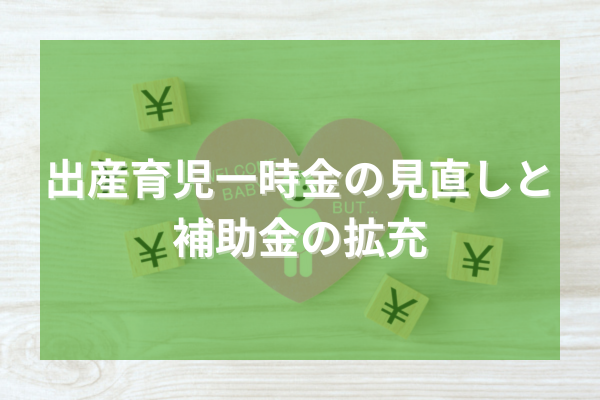
出産や育児に関連する補助金としては、以下の変更や新設が行われました。
- 出産育児一時金の支給額の増加:原則42万が原則50万円に増加
- 出生後休業支援給付金の新設:子どもが生まれた後の一定期間内に両親がともに14日以上の育児休業を取った場合に支給
- 育児時短就業給付金の新設:子どもが2歳未満の期間に時短勤務によって賃金が低下した場合に支給
出産費用に充てる出産育児一時金が13年ぶりに増加して、出産直後と時短勤務に対する補助金を開設しています。
それぞれの補助金の適用開始日と支給額は、以下のとおりです。
| 変更・新設 | 適用開始日 | 支給額 |
|---|---|---|
| 出産育児一時金の支給額の増加 | 2023年4月から | 原則50万円 |
| 出生後休業支援給付金 | 2025年4月から | 休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13% |
| 育児時短就業給付金 | 2025年4月から | 原則、育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給 |
※2025年7月時点
上記と併せて出生時育児休業給付金と育児休業給付金も申請できるため、出産前後で複数の補助金を利用できます。
出産や子育て応援交付金事業として伴走型相談支援や支援給付が行われる
こども未来戦略における新たな取り組みとして、以下の出産・子育て応援交付金事業が開始されました。
- 伴走型相談支援:妊婦や子育て世帯を対象に、保健師や助産師等が主産や育児に関する面談を行い、情報提供や支援を行う
- 支援給付:妊娠中と出産後にそれぞれ5万円ずつ、計10万円の経済支援を行う
さまざまな負担の多い出産前後の時期に、寄り添うような支援を行って、精神的や経済的に子育て世帯を支えます。
2023年2月頃から申請受付が開始され、2025年4月からは伴走型相談支援や支援給付が制度化されました。
支援給付の名称は市区町村によって異なる場合がありますが、妊娠中と出産後に支給される点は変わりません。
補助金以外にも無償化や生活環境の確保で子育てを支援する
補助金以外にも教育や医療費、住まいの援助制度として、以下の項目が利用できます。
- 大学等の授業料等減免支援拡大:扶養する子どもが3人以上かつ大学等に通っている場合、授業料70万円と入学金26万円までの範囲で無償化
- こども誰でも通園制度:0歳6ヶ月から満3歳未満の子どもを対象に、対応事業所への通園を月一定時間の範囲内で利用できる
- 医療費等の負担を軽減:地方自治体の医療費を対象に見直し
- 住まいの支援:空き家などの改修を行い、子育て世帯に適した住宅を確保する
- フラット35子育てプラスの金利負担軽減:子どもの人数に応じて金利引き下げ、金利引き下げ幅を最大年1.0%に拡充
上記に加えて、2026年からは自営業やフリーランスなどの国民年金第1被保険者に対して、保険料の免除措置を実行する予定です。
子育て世帯が利用できるこども未来戦略に関連する補助金の申請方法
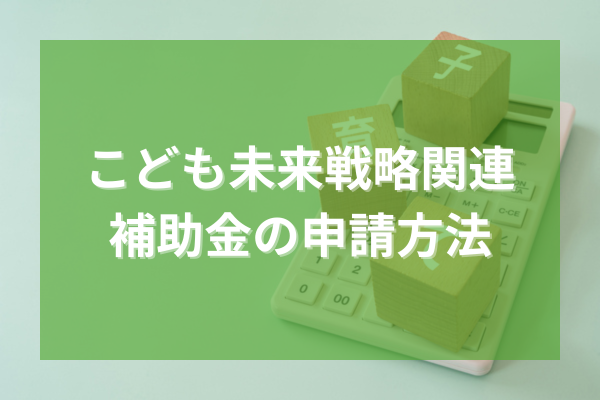
こども未来戦略で見直しや新設された補助金について、申請者や申請期限は、以下のとおりです。
| 補助金 | 申請者 | 申請期限 |
|---|---|---|
| 児童手当 | 養育者 | 出生日の翌日から15日以内 |
| 出産育児一時金 | 出産施設、もしくは両親 | 出産日の翌日から2年以内 |
| 出生後休業支援給付金 | 勤務先の事業主 | 併せて提出する書類による出生時育児休業給付金:出生日の8週間後から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで育児休業給付金:育児休業を開始する日から4ヶ月が経過する日が属する月の末日まで |
| 育児時短就業給付金 | 勤務先の事業主 | 支給対象月の初日から4ヶ月以内に初回申請する |
| 出産応援給付金 | 妊婦 | 医療機関で胎児の心拍が確認された日から2年間 |
| 子育て応援給付金 | 出生した子どもの母親、もしくは養育者 | 出産予定日の8週間前から2年間 |
※2025年7月
補助金の多くは子どもが生まれる前後で申請する必要があり、制度によっては期間が限られています。
児童手当は児童の状況によって父母以外も養育者に当てはまる可能性がある
児童手当における申請要件は、以下のとおりです。
- 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育する人
- 原則、児童が国内に住んでいる
- 父母の両方が児童を養育する:生計の主体となる年収の高いほうが申請者になる
- 離婚協議中で父母が別居している:同居する親が申請する
養育者は両親に限らず、以下のような状況では実際に養育する立場にある人が申請できます。
- 仕事都合で父母が海外に住んでいる:日本にいる祖父母を養育者に指定できる
- 養育中の児童が施設へ入所している:原則、入所施設の設置者が申請する
- 里親が児童を養育している:原則、里親が申請する
- 配偶者からのDV等で児童が避難している:児童と同居する人が申請する
子どもが留学以外で海外に住んでいる場合は、該当する児童の児童手当は支給されません。
一方、子どもが留学中で海外にいる場合は、以下のすべての要件を満たすと児童手当を支給できます。
- 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していた
- 教育を受ける目的で海外に居住し、父母と同居していない
- 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内である
留学中でも支給された児童手当は、両親の口座へ振り込まれます。
児童手当の申請窓口は通常は市区町村の役所で公務員のみ勤務先へ申請する
児童手当の申請時期は、生まれた子の人数にかかわらず、出生日の翌日から15日以内です。
出生日から15日以降も申請自体は可能ですが、原則、遅れた月分の手当が支給されません。
期間を遡っての支給や支給期間の延長には対応できないため、提出期限は遵守してください。
申請窓口は市区町村によって対応先が異なりますが、基本は以下のような施設が窓口として設けています。
- 各区役所の市民保険年金課や子育て推進課
- 各地域センター
- 各支所や出張所
一方、独立行政法人に勤める人を除く公務員の場合は、以下の2カ所に申請する必要があります。
- 現住所の市区町村
- 勤務先
公務員も申請が遅れた場合は、遅れた月分の手当を受け取れないため、忘れずに申請しましょう。
児童手当では別居中や多子加算を行う場合に追加で書類が必要になる
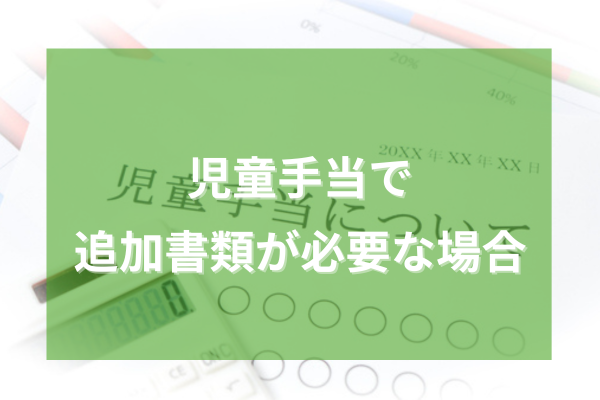
児童手当の申請における主な必要書類は、以下のとおりです。
| 多くの地域で必要になる書類 | 児童手当の認定請求書請求者名義で振込先口座情報がわかるもの請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの |
| 市区町村や申請者の状況によって必要な書類 | 請求者の健康保険証本人確認書類別居している場合:別居監護申立書多子加算を行う場合:監護相当・生計費の負担についての確認書 |
マイナンバーを提示する際にマイナンバーカードを使用する場合、市区町村によっては本人確認書類の提出を省けます。
上記以外にも児童手当の支給要件を確認するために書類の提出を求められた際は、準備して提出しましょう。
特定の状況に当てはまる人は児童手当の現況届を提出する必要がある
現況届は児童手当の支給要件を満たしているか確認するために、申請者が提出する書類です。
以前はすべての児童手当の受給者が対象でしたが、2022年6月以降の申請分から原則、現況届を提出する必要がなくなりました。
ただし、以下の状況や申請先の市区町村から現況届の提出を求められた場合は、提出しなければいけません。
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 支給要件児童の戸籍がない
- 多子加算の対象になる無職や社会人等の学生以外の子どもがいる
- 離婚協議中、または調停中のため配偶者と別居している
- 里親、施設等受給者
- 児童の父または母以外の養育者
- 配偶者からのDV等で児童が避難して、住民票の住所と異なる場合
現況届を提出しないと支給要件を満たす証明ができないため、提出が必要になった際は必ず対応しましょう。
児童手当はマイナポータルからオンライン申請が行える

児童手当は支給要件を満たしたうえで、以下を所持している場合はマイナポータルからオンライン申請が行えます。
- 有効なマイナンバーカード
- NFC対応スマートフォン、もしくはICカードリーダライタ
申請時にマイナンバーカードの読み取りが必要になるため、スマホの場合は読み取り機能がある機種が必要です。
パソコンから申請する際にICカードリーダライタがない場合も、画面上のQRコードをスマホで読み込んで書類を提出できます。
具体的なオンライン申請の手順は、以下のとおりです。
- スマホかパソコンにマイナポータルのアプリをダウンロードする
- マイナポータルに署名用電子証明書のパスワードを入力後、マイナンバーカードを読み込む
- マイナポータルを初めて利用する場合は、メールアドレスの登録や確認コードを入力して利用者登録を行う
- 登録後、「さがす」のキーワード検索欄に「児童手当」と入力して検索する
- 検索結果から「児童手当 認定請求書」など、該当する申請を選ぶ
- 概要や必要書類などの申請内容を確認して「申請する」を選ぶ
- 「電子署名の動作環境確認」から申請で使用する機種や書類などを選ぶ
- 添付書類を選んだ方法で読み込んで、アップロードする
- 申請完了
パスワード入力やマイナンバーカードの読み取りは複数回行う場合もあるため、手続き中はすぐに片付けずに手元へ置いておきましょう。
公務員は就職や離職の状況によって児童手当の申請や変更手続きが必要である
公務員は以下の状況に当てはまった場合、現住所の市区町村と勤務先へ児童手当の手続きを行う必要があります。
- 児童がいる状態で新たに公務員として採用された場合
- 所属する官署等を異にして異動した場合
- 公務員として勤務する間に子どもが生まれた場合
- 現況届を提出する場合
- 氏名の変更や住所地の変更があった場合
転職で新たに公務員になった人や、異動になって引き続き児童手当を受給する場合は、現在の勤務先へ申請が必要です。
申請時の情報から変更があった場合は、勤務先が変わっていなくても、情報を更新しなければいけません。
一方、公務員だった人が退職した場合は、公務員でなくなった日の次の日から数えて15日以内に現住所の市区町村への申請が必要です。
出産育児一時金は3種類の受け取り方法から選べる
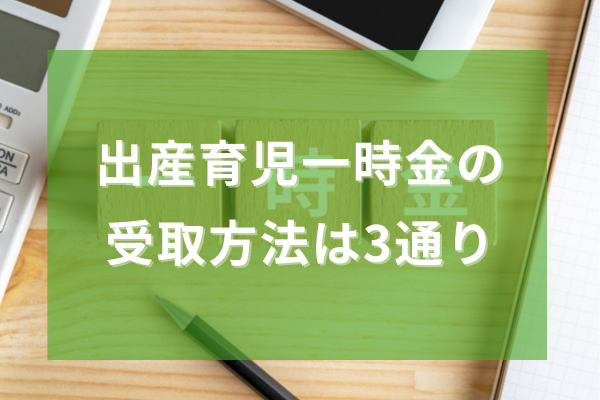
出産育児一時金の支給対象になるのは、以下の要件を満たす人です。
- 出産した時点で日本の公的医療保険に加入している
- 妊娠4ヶ月(85日)以上の出産である
- 妊娠4ヶ月以上であれば、早産や死産、流産や人工妊娠中絶でも支給対象
- 海外で出産した場合、出産時点で有効な加入資格を有していれば支給対象
出産育児一時金は補助金の受け取り方法を、以下の3種類から選べます。
- 直接支払制度:出産施設が被保険者に代わって申請を行い、出産施設が補助金を受け取る
- 受取代理制度:被保険者自身が申請を行い、出産施設が被保険者に代わって補助金を受け取る
- 償還払い制度:被保険者自身が申請を行い、そのまま補助金を受け取る
出産施設が補助金を受け取った場合、出産費用に充てる形で相殺されて、足りない金額分は支給対象の人に請求します。
一方、出産費用の総額が支給額を下回る場合、被保険者は保険会社に対して差額の請求が可能です。
直接支払制度は施設によって対応できるか異なるため、制度を利用する際は施設側に確認しましょう。
償還払い制度を選んだ場合は支給が出産費用の支払い後になるため、出産施設で一旦出産費用の全額を支払う必要があります。
出産育児一時金は直接支払い制度で出産施設との合意書が必要である
出産育児一時金の申請に必要な主な書類は、以下のとおりです。
| 共通で必要な書類 | 出産した母親の本人確認書類預金通帳や振込先の確認ができるもの母子健康手帳医療機関等で発行される出産費用の領収・明細書手続きする人の本人確認書類 |
| 直接支払制度 | 出産施設等と交わした直接支払制度代理契約に関する合意書 |
| 受取代理制度 | 受取代理用の出産育児一時金等支給申請書直接支払制度を利用しない旨を証明する書類 |
| 償還払い制度 | 直接支払制度を利用しない旨を証明する書類 |
※2025年7月時点
直接支払制度は出産施設等で制度の利用に関する同意書を作成して、提出する必要があります。
出産施設側で同意書の用意ができない場合や記入を拒否された場合は、申請できません。
残りの2種類は二重支給を防ぐために、直接支払制度を利用しない旨を証明する書類を求める場合があります。
出産育児一時金は受け取り方法ごとに申請手順が異なる
直接支払制度の申請手順は、以下のとおりです。
- 出産前に出産施設で申請者が直接支払制度を利用する意思を確認し、施設側が利用に関する合意書を作成する
- 出産のために入院する際、公的医療保険の有効な加入資格があるか確認する
- 出産後、出産費用の明細が発行される
- 問題がなければ保険者から被保険者に支給決定通知が送付される
- 出産費用の総額が出産育児一時金の支給額を下回る場合は、保険者に差額を請求できる
合意書を作成した後は、出産後に施設側が手続きを代行します。
受取代理制度の申請手順は、以下のとおりです。
- 出産前に加入中の保険の公式サイト等から出産育児一時金の支給申請書を取得する
- 出産施設に対して、支給申請書の受取代理欄の記入を依頼する
- 記入すべき箇所をすべて埋めた後、支給申請書を保険者に提出する
- 出産後、出産施設から出産費用請求書と出生証明書が発行される
- 出産費用の総額が出産育児一時金の支給額を下回る場合は、保険者に差額を請求できる
書類の準備は保険者側で行い、提出後は直接支払制度と同じように手続きが進められます。
償還払い制度はほかの受け取り方法を利用しなかった場合に、出産した人が住民登録をした市区町村で申請手続きを行えます。
申請先は市区町村の役所や支所にある国保の窓口であり、市区町村によっては必要書類の郵送のみでも申請が可能です。
出生後休業支援給付金はひとり親や配偶者が自営業の場合でも申請できる
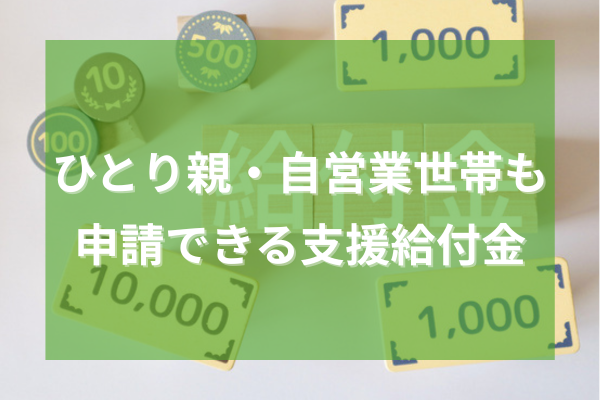
出生後休業支援給付金の支給には、父母がともに以下の要件を満たす必要があります。
- 父親:出生後8週間以内に産後パパ育休、または育児休業を通算して14日以上取得
- 母親:産後休業後8週間以内に通算して14日以上の育児休業を取得
ただし、出生日の翌日で以下のいずれかの項目に当てはまった場合、上記の要件を満たさなくても申請できます。
- 配偶者がいない
- 配偶者が勤務先で3ヶ月以上の無断欠勤を継続する、または災害により行方不明
- 配偶者が被保険者の子どもと法律上の親子関係がない
- 被保険者が配偶者から暴力を受けて別居中
- 配偶者が無業者
- 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
- 配偶者が産後休業中
- 日々雇用される者など、上記以外の正当な理由で配偶者が育児休業できない
配偶者が家事専業の家庭や何らかの理由でひとり親の状況でも、育児休業できない正当な理由がある場合は申請が可能です。
申請手続きは原則、勤務先の事業主が出生時育児休業給付金、または育児休業給付金の支給申請と併せて行います。
必要書類は市区町村によって異なりますが、労働者側は主に以下のような書類の提出が必要です。
- 母子健康手帳
- 住民票
- 出産予定日証明書などの医師の診断書
上記以外にも、事業主から両親や子どもが支給要件を満たしていると証明するための書類を求められた場合は、対応しましょう。
育児時短就業給付金は4つの要件をすべて満たす月に支給される
育児時短就業給付金を受けるためには、以下の2つの要件を満たさなければいけません。
- 2歳未満の子どもを養育するために育児時短就業する雇用保険の被保険者である
- 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始する、または育児時短就業開始日前2年間に被保険者期間が12か月以上ある
上記を満たしたうえで、以下の要件をすべて満たす月に給付されます。
- 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月
- 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
- 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
- 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
申請手続きは原則、勤務先事業主が育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認及び支給申請を行います。
労働者は2歳未満の子どもの養育を証明するために、母子健康手帳等のコピーなどの提出が必要です。
勤務状況を示す賃金台帳や出勤簿は事業主側で用意できますが、労働者側で書類の記入や提出する必要がある場合は対応しましょう。
出産応援給付金と子育て応援給付金はそれぞれ面談を経て申請書をもらう
出産応援給付金と子育て応援給付金は同じ応援交付金事業として扱われますが、対象者や申請期限が異なります。
| 出産応援給付金 | 子育て応援給付金 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 市区町村の指定した年度以降に妊娠届出を出した妊婦流産や死産、人工妊娠中絶等も対象 | 市区町村の指定した年度以降に生まれた子どもを養育する人 |
| 支給額 | 妊婦1人あたり5万円 | 子ども1人あたり5万円 |
| 申請期限 | 医療機関で胎児の心拍が確認された日から2年間 | 出産予定日の8週間前から2年間 |
※2025年7月時点
基本は現金を振り込みますが、市区町村によっては5万円相当のギフトカードを選択できる場合があります。
出産応援給付金の申請手順は、以下のとおりです。
- 妊娠届提出時に保健所等の窓口で応援給付金の利用について相談する
- 保健師や助産師等が妊婦と面談を行う
- 面談後に申請書が渡されて、必要事項を記入した後、郵送する
- 申請が認められた場合は給付金が振り込まれる
妊娠届出を提出した際に保健所側から案内される場合もありますが、案内がなかった際は給付金について窓口で確認しましょう。
一方、子育て応援給付金の申請手順は、以下のとおりです。
- 出産後に保健所等の窓口や家庭訪問で応援給付金の利用について相談する
- 保健師等が母親と面談を行う
- 面談後に申請書が渡されて、必要事項を記入した後、郵送する
- 申請が認められた場合は給付金が振り込まれる
伴走型相談支援により保健師等が家庭訪問する場合は、訪問時の面談で申請書も入手できます。
補助金や支援制度を正しく理解して利用すると負担を軽減できる
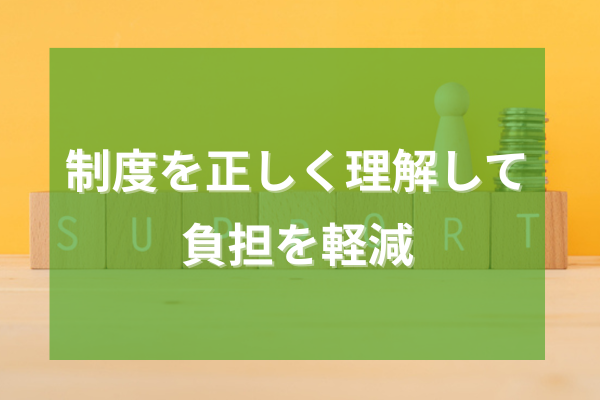
子育てに関する補助金や支援制度に対して、利用や申請をするのが恥ずかしいと感じる人もいるでしょう。
しかし、補助金や支援制度は国が用意した正当な支援であり、要件に該当する人は利用する権利があります。
子育ては精神的な負担を感じるときがあり、経済面でも余裕がなくなると仕事や育児に影響が出てきます。
周りの目が気になる人も精神的、経済的に負担を感じている場合は、自分が利用できる補助金や支援制度を利用してください。
補助金や支援制度によりお金や心に余裕ができた場合、以下のような効果も期待できます。
- 精神的な負担の軽減から、穏やかな気持ちで育児を行える
- 経済的に余裕がある場合、習い事や教材など、子どもの教育への投資が増える
- 十分な食事や適切な医療を受診できて、子どもが健康的に成長できる
- 生活レベルの向上から、子どもが良い環境で生活できる
- 制度に付帯する相談窓口や支援団体の利用で子育てにおける孤立が防止される
制度を申請する際の窓口への相談や補助金の要件に含まれる面談から、子育てに関する親の悩みも話せる機会が増えます。
子育て世帯が利用できる補助金を有効活用してさまざまな負担を軽減する
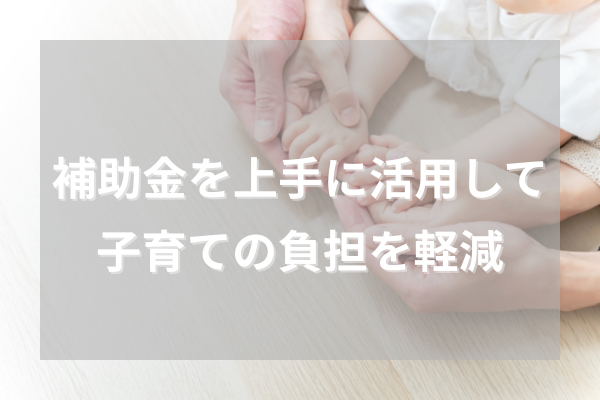
子育て世帯が利用できる補助金の変更点や新設された制度をまとめると、以下のとおりです。
- 児童手当は所得制限がなくなり、高校生年代まで支給するように見直された
- 出産一時金の支給額が原則50万円に引き上げられた
- 出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が2025年4月から新設された
- 2025年4月に出産、子育て応援交付金事業が制度化された
- 補助金や支援制度は国が用意した正当な支援である
- 補助金の利用で精神的、経済的な余裕ができると、子育てにも良い影響がある
子育てに関連する補助金は支給範囲や金額などが、利用者に寄り添う形で見直されています。
各種補助金で申請方法や必要書類が異なる点は大変ですが、要件に当てはまる補助金は活用してみてください。

